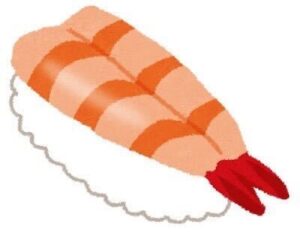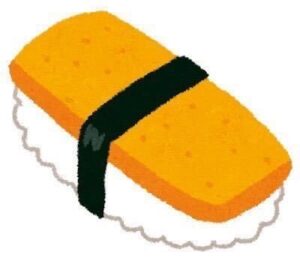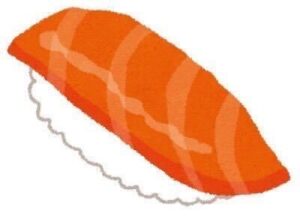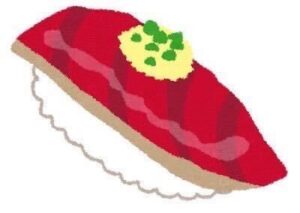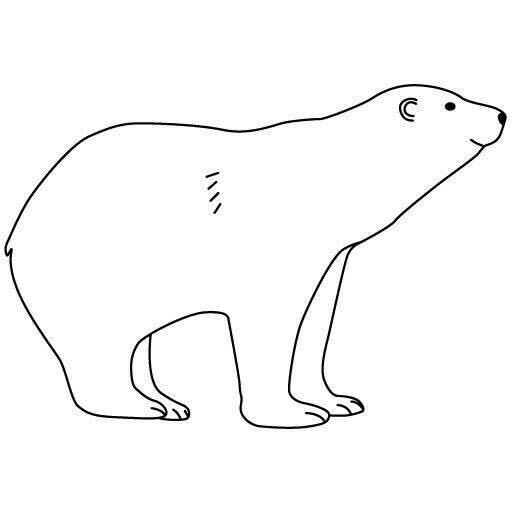2025年度に卒業研究として取り組むことをお勧めしたいテーマをまとめると以下のようになります.
関根研究室では,教員と学生とのミーティングを大事にしており,共同研究者として議論を重ねつつ研究を前へ進めていくことにしています.
テーマの中核となるのは,水の流れ・河川地形の変化・自然豊かな河道の創造と,豪雨・洪水氾濫・高潮による浸水ならびに水災害の予測のふたつです.いずれも現象をできる限り力学原理に忠実に踏まえて解明あるいは理解することを目指しています.
さらに,すでに解明されている知見や予測手法を駆使して,減災を実現する新たな技術や災害に強い都市の創造,自然豊かな河川空間のあり方などについて研究しています.
研究室としてはこれまでにない新しいテーマを発掘しチャレンジしてきていますので,下記のもの以外にテーマを見出している人やテーマを決めかねている人は,相談を持ちかけてもらえれば幸いです.
1.「都市で発生する大規模浸水・地下浸水のリスク評価と群衆の避難誘導,豪雨に強いまちづくり」
極端気象の表れとして近年記録的な豪雨が発生していますが,当研究室では,2021年度から10年計画で行われている文部科学省DIASプロジェクトの研究課題に採択され,2022年9月1日から「豪雨時に発生する浸水をリアルタイムに予測するシステムS-uiPS (Sekine’s urban inundation Prediction System)」の先行公開が始まりました.2025年度は中野区と連携した社会実験を行う予定で準備が進んでいます.
東京には大規模な地下空間が多数存在しており,これらが都市浸水時の弱部となることから,地下鉄駅の浸水やトンネルを通じた氾濫水の拡大が生じると重大な結果を招くことになります.2025年度は首都高速道路と連携して地下環状線の浸水発生のメカニズムと,被害防止・軽減の方策を探る研究を始めます.地下空間に関しては,これまで取り組んできた渋谷と丸の内の検討に加えて,2025年度には新宿と八重洲の地下空間を対象にした研究に着手する予定です.
このほか,東京都23区と横浜市・川崎市に加えて,次にS-uiPSを適用していく先として政令指定都市の札幌市を候補とすることにし,その浸水リスク評価とリアルタイム浸水予測の実現を目指して研究を行うことを考えています.これ以外に,住民が見て直感的に浸水リスクを理解できる動画の表現方法の研究や,VRやARを活用した仮想体験に関する研究にも取り組んでいきます.
- (1) 東京都23区の豪雨時リアルタイム浸水予測システムの社会実装に関わる研究
- (2) 東京以外の政令指定都市(札幌市)へのS-uiPSの展開と同市の豪雨災害予測
- (3) 火山灰で覆われた東京都23区の豪雨時大規模浸水予測と激甚災害発生シナリオの検討
- (4) 大規模地下空間を対象とした浸水リスク評価と避難誘導シミュレーションに基づく誘導戦略
- (5) 浸水リスクに関わる住民の理解向上を実現する浸水情報の表示・伝達技術に関わる研究
2.「河川の自律形成機能の解明と河道再生を可能とする数値予測技術の開発」
水流による土砂移動 (すなわち「流砂」) のメカニズムには未だに解明できていない課題が多く残されているにもかかわらず,すでに十分な理解が得られていると錯覚している研究者や技術者が多数存在し,計算を行いその結果を完全に信じて疑わないという風潮すらあるように思われます.これに対して,早稲田大学では前任の吉川先生の時代からこの分野の研究をリードし,独自性の高い研究を続けてきました.今求められているのは洪水時にも何とか対応できる「可能な限り自然豊かな河道」を創出していくことであり,そのためには「河道の自律形成機能」についての力学的理解が必要です.
このため,当研究室では,様々な観点から多くの基礎実験を積み重ね,そこから得られた科学的な知見を踏まえて,新たな河道再生技術を創り出していくことを目指しています.また,これまでになく精緻にこの変動を予測するシステムの開発も目指しています.
- (6) 粘土河床と砂礫河床の相互転移メカニズムの解明とその数値予測
- (7) 流砂理論の再構築を目指した移動床実験と数値シミュレーションによる現象の解明
- (8) 河川堤防の決壊メカニズムの解明とその数値予測
- (9) 河道の自律形成機能に及ぼす植生の影響の解明と自然豊かな河道再生に向けた研究
- (10) 神奈川県酒匂川を対象とした置き砂が河道再生に及ぼす影響に関わる数値予測
3.お知らせ
説明会の日時以外であってもご相談に応じたいと思います.何かありましたら遠慮なくこちらにメールを送ってください.